まずは抜粋
風のように迅速に進み、林のように息をひそめて待機し、火の燃えるように侵奪し、暗闇のようにわかりにくくし、山のようにどっしりと落ちつき、雷鳴のように激しく動き、村里をかすめ取って兵糧を集めるときには兵士を分断させ、土地を奪って広げるときにはその要点を分守させ、万事についてよく見積もりはかったうえで行動する。
釣訳
風のようにポイントに到着し、林のように息をひそめてキャストし、火の燃えるようにフッキングし、暗闇のように・・・・○▽◇✖し、山のようにどっしりと落ちつき、雷鳴のようにタモを落としこむ。力尽き。
言わずと知れた『孫子の兵法』。戦や戦争のバイブル。特に理由は無く何故か突然読みたくなった本。
他にも有名なもので『戦わずにして勝つ』や、『百回戦闘して百回勝つのはすぐれたのもではなくて、戦闘しないで敵を屈服させつのが最高にすぐれたこと』等があります。
ほいで
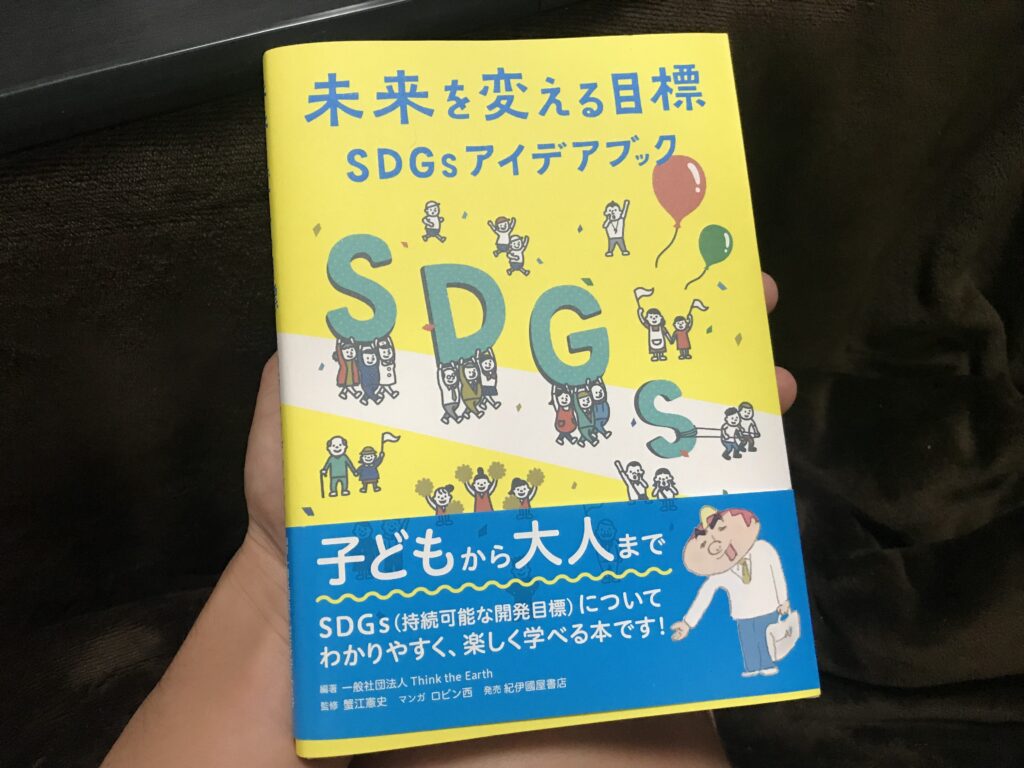
こっちの方は読み終わりました。※かなりのスローペース
おもしろいな~と思ったのは、社会や自然へ悪影響を与えている会社に出資している銀行へはお金を預けない。みたいな運動で、これもSDGsの一つらしい。
海の話しだと、密漁や生態系の事を考えずに漁獲された魚は買わないという選択がSDGsになるとの事。持続可能な漁業で獲られた水産物にはMSC認証というマークがついていて、このマークがついている魚を買うだけで海のため、自然の為になる。
まぁ実際そこまで考えて買うほどの意識は中々難しいですが、売る側としてはMSCマークがあることで海外との取引に有利になるらしいです。
※海外の資源管理は日本よりとても進んでいて、漁獲方法にもとてもこだわっている。
ちなみに絶滅危惧種のウナギの流通は、ほぼ真黒の闇社会。
とりとめのない記事で申し訳ありませんが、何が言いたいかというと
読書の秋 ✖ → 読書の梅雨 〇
次は孔子の『論語』だな
よく言う、子(し)いわくナニナニ~の子(し)が、この孔子。
梅雨明には悟りを開いている予定。


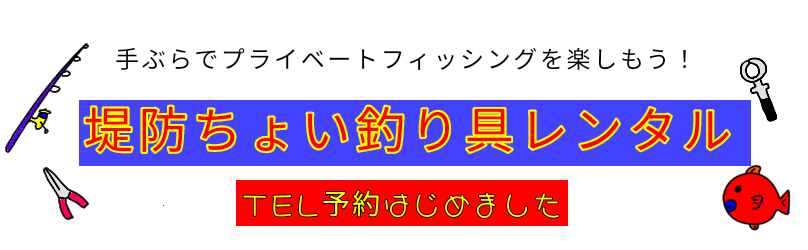



ウナギのシラスに関して言えば、漁業組合の人間も、ノルマをクリアしたら残りは闇に流した方が金になるって言ってましたからね。
漁業組合の人間は海に対して真摯に向き合っているかと思えば、そうではないなぁと感じるところがあります。
沖に出ると平気でゴミ捨てたり(^_^;)
難しい所です。
貴重なお話ありがとうございます!
漁業組合の方の気持ちは十分わかるのですが、それが長期的にみて自分達の首を絞めている事になるんですよね。(※勉強したばかりなのに偉そうな事言ってすみません)
やはり沖は無法地帯なんですね。。
罰則を厳しくすればなくなるっていうものでも無さそうですし、真面目にやってる人が損をするシステムじゃ魅力も感じないですよね。
何かいい方法があればいいのですが、、、要勉強ですね。。